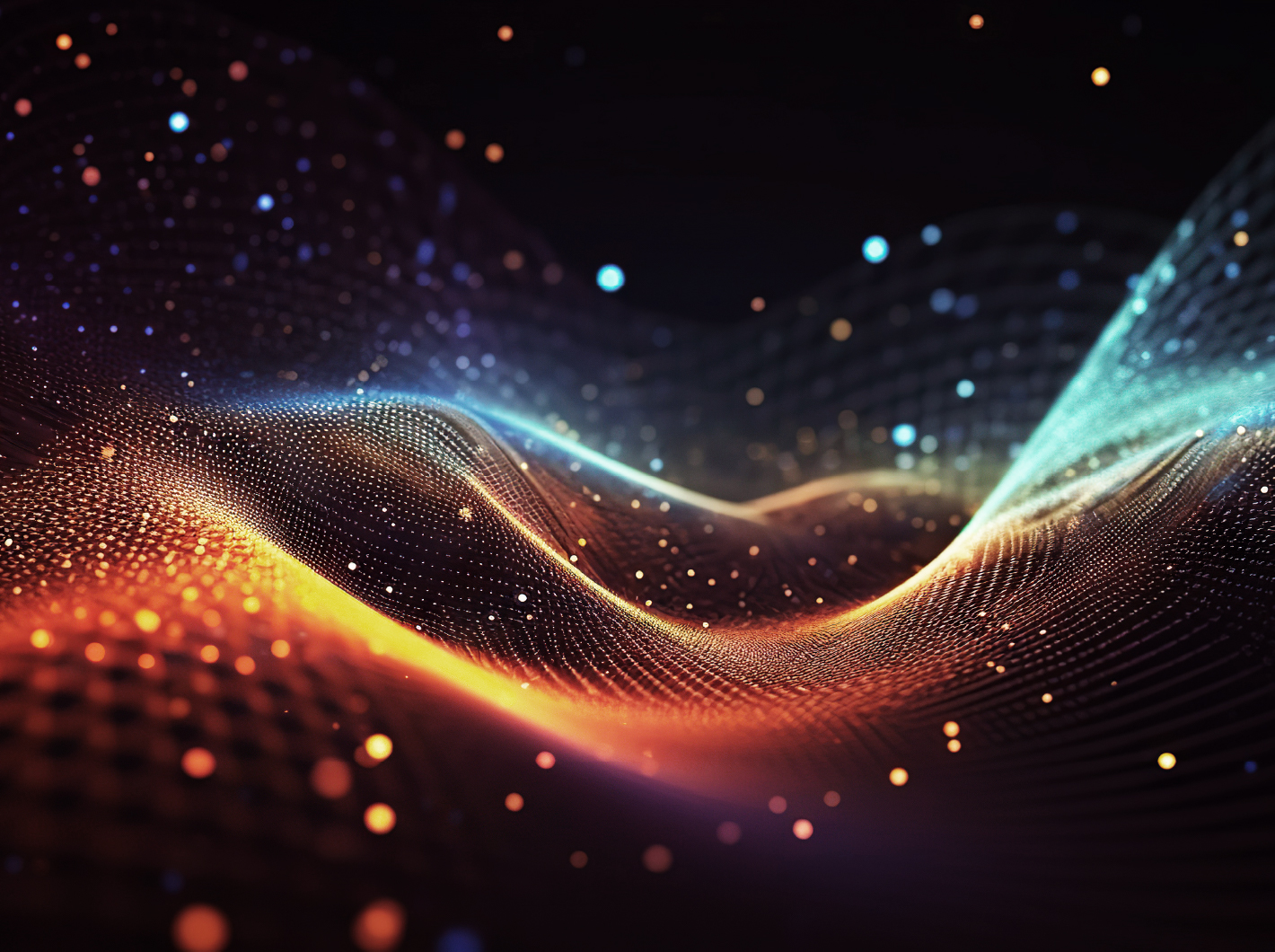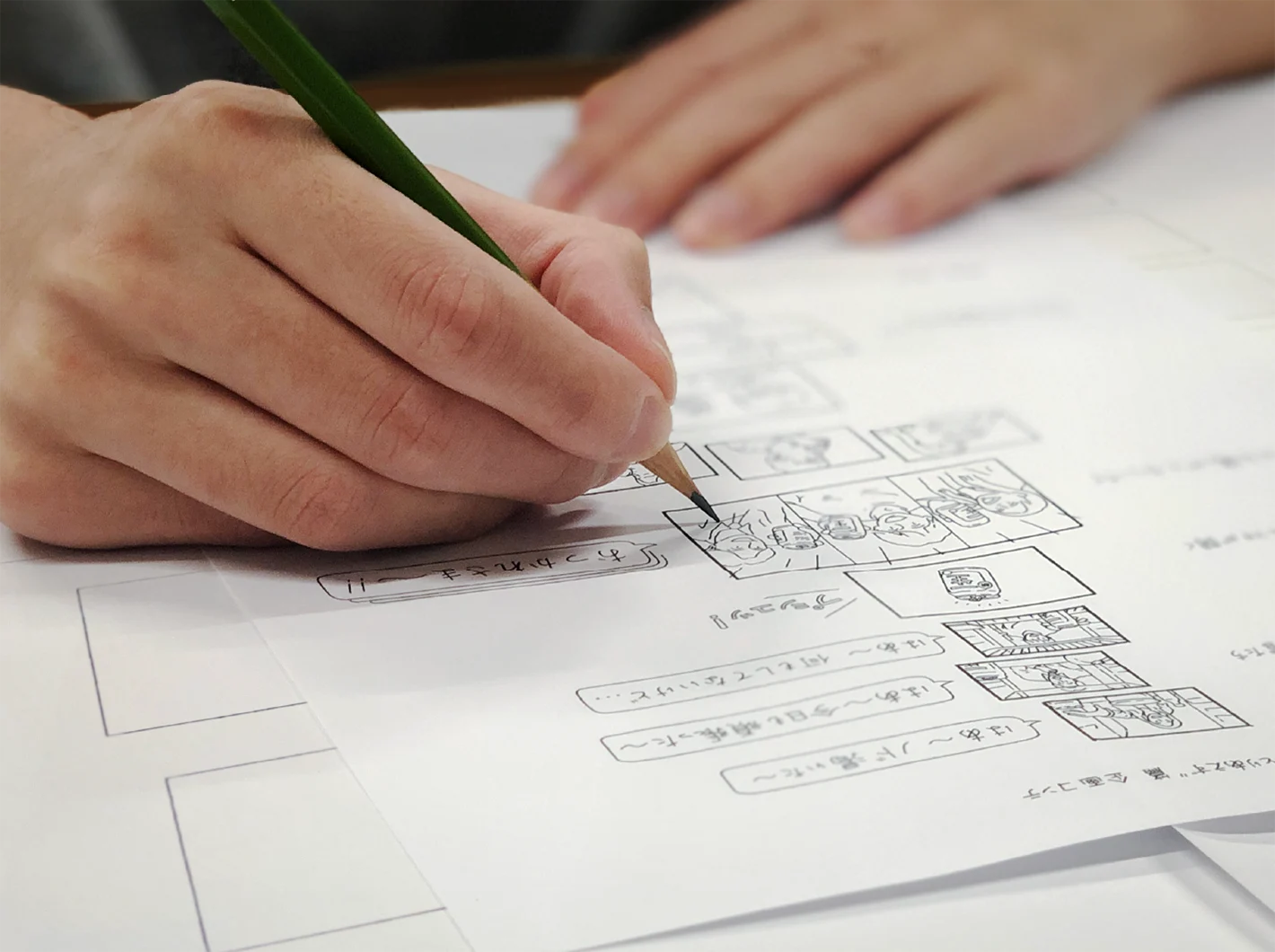2025.09.09
伝わらないもどかしさが、私を映像へと連れていった ─「伝えるのが苦手だった私」の遠回りな選択
- LIGHT THE WAYのこと
はじめまして。2025年4月に新卒で入社しました、藤井玖光(ふじい くみ)です。
出身は兵庫県神戸市。そんな私が関西から東京に出てきて、映像の仕事を選んだ理由をお話ししたいと思います。
その原点には、かつての自分が抱えていた「言いたいことがあるのに、うまく伝えられない」という感覚がありました。たとえば、友達と話しているときに、なんとなく会話が噛み合わなかったり、自分なりに大切に思っていることを言葉にしても、うまく届いていない気がしたり。真剣に話しているつもりなのに反応が薄かったり、話題をすぐ変えられてしまったり。そんな経験を何度か重ねるうちに、いつの間にか「伝えること」に慎重になっていた気がします。
時間をかけて話せば、きっと気持ちは届く。わかり合える。そう思っていても、その一歩手前で気持ちがすり抜けてしまうような感覚がありました。もっとスムーズに、自然に、思いを伝えられたら。そんなもどかしさが、ずっと心の奥にあったんだと思います。
人前で話すのが極端に苦手なわけではありません。ただ、自分の考えや気持ちを言葉にするのが難しくて。話しているうちに何を伝えたかったのか分からなくなったり、相手の反応が気になって途中で言葉を飲み込んでしまうことも、少なくありませんでした。でも、それは「伝えたいことがない」わけじゃない。どうすれば、自分の思いをちゃんと伝えられるのか。その答えを、ずっと探し続けてきたように思います。
今回は、そんな私が「映像で伝える」という手段に出会い、この仕事を選ぶまでの過程を振り返ってみたいと思います。
思考することからはじまる、私のものづくり
私にとって中学校は、初めて「自分の外側に広がる世界」を意識しはじめた場所でした。
小学生の頃までは、似たような感覚や価値観を持つ友人たちとだけ過ごす、穏やかで心地よい日々が続いていました。自分の考えがそのまま「世界の当たり前」として通用する、ある意味で守られた空間の中にいたのだと思います。
けれど中学に進学すると、少しずつ目に入ってくる世界が変わり始めました。自分とは異なる価値観や考え方、ふだんのふるまいや発言から見える「他者のふつう」に直面するなかで、私の中に漠然とした違和感が生まれました。以前は、自分が良いと思うものは誰かと共有できるのがあたりまえだと思っていたのに、あまり興味を持ってもらえなかったり、「へぇ〜」で終わってしまったり。そんな「共感されない」という感覚だけが残ってしまう。
今思えば、思春期の真っただ中で「他者と自分の違い」に敏感になっていったのだと思います。けれど当時の私は、その違和感の正体がわからず、「違う考えを持つことは、きっと間違っているのではないか」と、心のどこかで思い込んでいたように思います。その思い込みは、やがて自分の考えや気持ちを外に出すことへの苦手意識やコンプレックスにつながり、「表現すること」の見えないハードルになっていました。
その一方で、自分の考えや感じたことを、誰かに知ってほしいという気持ちも心の中にはあり、そのふたつの思いのあいだで、私は揺れていました。

そんな矛盾を抱えていた私に小さな変化をもたらしてくれたのが、所属していた放送部で取り組んだ中学卒業記念の映像制作でした。
同級生や先生へのインタビューを通して思い出をまとめるという内容で、企画から撮影、編集まで、すべてが初めての体験でした。SDカードからデータを取り込む方法すら分からず、「MP4ってなに?」という状態からのスタート。映像編集ソフトや機材の使い方も何もかも手探りの中で完成した映像。それを見た友人が「よかったよ」と声をかけてくれた瞬間、それまでうまく言葉にできなかった気持ちが、映像を通せば届けられることに気づきました。
言葉だけでは伝えきれなかった内面を思考を重ねて構成し、映像として外に出す。私を表現することへの手ごたえを感じることができた出来事でした。この経験をきっかけに、私にとって「映像」は単なる技術や表現手段ではなく、思考を通じて他者とつながるための、自分にとって自然で信頼できる「ことば」になっていったように思います。
映像制作から見えた、枠を飛び越えた先の世界
その後、映像制作を始めた私は、高校生のときに、あるIT教育のイベントに参加しました。それは、大学生のメンターたちが中高生にITスキルを教えてくれるというイベント。
「技術を学びたい」という興味から足を運んだ私でしたが、いちばん印象に残ったのは、スキルそのものではなく、教えてくれた大学生たちの姿でした。彼らは、まっすぐに「好き」や「関心」に向き合いっていました。誰かと違っていても臆せず、自分の思いや考えを自然に表現していたのです。当時の私は、映像への関心を誰かに打ち明けることすら、少し怖さを感じていた時期でした。「みんなと同じ」でいることを普通だと思い込み、夢中になっている自分は「ずれている」のではないかと不安に思っていたのです。
そんな私にとって、大学生メンターたちの姿は、自分のなかで「ふつう」だと思っていた枠組みを壊してくれるようなものでした。世界はもっと広く、たくさんの「ふつう」があっていいのだと、背中を押してくれた体験でした。
「伝える」から「伝わる」表現へ
映像制作を続けた高校の3年間は、そんな私にとって大きな学びと変化の連続でした。
日々の制作を通じて、多くの人と出会い、さまざまな経験を積み重ねるなかで、いつしか中学の頃に感じていた「表現への苦手意識」や「自分への不安」は、少しずつほどけていったように思います。
そうしたなかで、大きな転機となったのが、高校最後の年に取り組んだドキュメンタリー番組の制作でした。番組の内容は性的マイノリティの方へのインタビューを通じて、多様性について考える内容でした。制作当時はコロナ禍。部室での作業ができず、自宅からオンラインでミーティングや取材を重ね制作した作品でした。そんな作品が学校内だけでなく、地域の人々やSNSを通じて広がっていく様子を目にしたとき、「自分の発信が誰かに届き、心を動かすことができる」そんな表現の可能性に改めて深いおもしろさを感じました。
けれど同時に、「ただ伝えたいことを並べるだけでは、本当に伝えたいことは届かないのではないか」という違和感も芽生えました。
それは、おそらく中学時代に感じていた、想いを言葉にできずもどかしかった記憶とどこかでつながっており、表面的な情報ではなく、もっと内面的なものが伝わる表現をしたい。そんな想いがいつの間にか育まれていました。
ただ情報を発信するのではなく、どうすれば相手の立場に立って、分かりやすく、人に届けることが出来るか。その工夫こそが、私が映像をつくるうえで一番大切にしたいことなのだと気づいたのです。
この気づきは、今の私のものづくりの軸を作るうえでの原点となっています。

思考がもたらす変化
こうして映像を「自己表現のための手段」から、「物事の本質を捉え直し、誰かに伝えるための道具」としても捉えるようになった私は、大学に進学してからも学業の傍らで映像制作を続けていました。同時に、かつて教わる側として参加したIT教育イベントを運営する会社でメンターとして活動するようになりました。
メンターとして出会った中高生たちは、趣味も関心もさまざまで、ひとりひとりがまったく違う価値観を持っていました。私は彼らに唯一無二の体験を届けたい、そんな思いを胸に向き合っていました。実際に中高生の前に立っていると、最初は緊張した表情で参加していた彼らが、イベントの終わりには自分の好きなことを楽しそうに語り、笑顔が増えている姿が見られました。
それは、メンター活動の原動力になったともに、これまでは映像を通じた情報発信や自己表現にのみ思考の価値を見出していた私自身が、人の行動や想いに対して思考を重ねることへの魅力にも気づくきっかけになりました。
思考することからはじまる、価値のあるものづくり

今、私がものづくりと向き合ったとき、最初に思うのは「これって、誰にとって、どんな意味があるんだろう?」という問いです。
それは、自分自身が伝えることが苦手だった頃に抱えていた違和感や、うまく言えなかった思いとずっと向き合ってきたからこそ、持つようになった視点かもしれません。
「伝えられない自分」を責めていたあの頃から、いくつもの経験をしてきました。
しかし映像制作をきっかけに、思考を重ねて形にすればちゃんと誰かに届くことを知り、その体験が表現することの面白さを教えてくれました。
そして、大学生のメンターたちとの出会い、イベントで出会った中高生たちとの関わりのなかで、「伝える側」と「受け取る側」の両方の視点が、自分の中でつながっていきました。
思えばどの体験も共通していたのは「思考」でした。伝わらなかった経験も、伝わった経験も、その背景には必ず「何を、どう伝えるか」を考えたプロセスがありました。私は、「ものづくりは、考えることから始まる」と思っています。 そして映像はそのアウトプットするためのツールであると。
私にとって映像とは、単に表現する手段ではなく、思考と共感をつなぐ翻訳ツールのようなものです。 「正しく伝える」ことではなく、「相手の視点に立って、伝わる形に変換する」。
それを、映像の力を借りてやっていく。そんなものづくりを、私はこれからも続けていきたいと思っています。
映像制作という仕事を選んだ理由の根底にあるのは、「考えすぎてしまう自分を、肯定したかった」という気持ちなのかもしれません。たくさん悩み、考えたからこそ、伝えられることがある。
遠回りしてきたからこそ、気づけたことがある。そう信じられるようになった今、思考することを恐れずに、そして、誰かの思考にも寄り添えるような表現をしていけたらと思います。